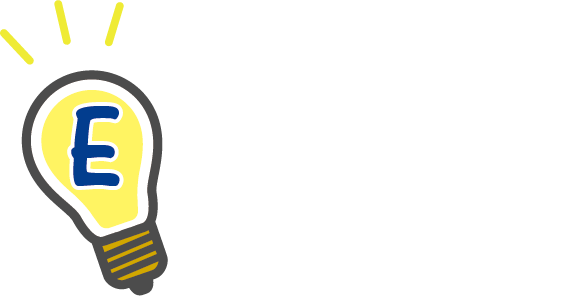SPLリファレンス
内容紹介
SPLリファレンス
このコースでは、よくある質問や開発現場で得られたコツ、Tips、事例などを紹介します。
以下では、コンテンツの先頭部分を少しお見せします。リンク先は有料コースです。一部のコンテンツは体験版として公開しており、無料会員登録で

《SPL開発支援ツール(有償)》
| コンテンツ名 | 内容 |
|---|---|
| 【未】pure::variantsの紹介 | <続きを見る> |
《SPL開発支援ツール(OSS)》
| コンテンツ名 | 内容 |
|---|---|
| featureIDEの紹介 | この講座では、SPL開発を支援する、featureIDEというツールについてご紹介します。 featureIDEとはfeatureIDEとは、SPL開発における、可変性分析とコンフィグレーションをサポートするツールです。featureIDEは以下の機能を有しています。・ツリー形式でフィーチャモデルを定義する・フィーチャモデルで定義されたフィーチャを選択することで、コンフィグレーションモ... <続きを見る> |
《SPL開発支援ツール(eXmotion内製)》
| コンテンツ名 | 内容 |
|---|---|
| assetExtractor & Addinsの紹介 | この講座では、SPL開発を支援するエクスモーション製のツールであるassetExtractorと各種Addinについてご紹介します。 エクスモーション製ツールのご紹介エクスモーションもSPL開発をサポートするツールをご用意しています。ツールにはassetExtractorと、各種Addin(Excelアドイン、Wordアドイン、EAアドイン、…)があります。本ツールは、f... <続きを見る> |
《可変性分析・フィーチャモデリングのポイント》
| コンテンツ名 | 内容 |
|---|---|
| 全てのフィーチャを表現しない | この講座では、フィーチャモデルのフィーチャを分析する際の大切な考え方を紹介します。 フィーチャとはまずはフィーチャモデルに関連する用語について、簡単な復習を行いましょう。フィーチャモデルを構成するフィーチャとは、製品の特徴・特性のことで、これらのバリエーションを管理することがSPL開発のキモとなります。抽象的な要求相当のフィーチャから、コードの定数に至る細かなレベルのフィーチャまで存在... <続きを見る> |
| 抽象フィーチャを使って整理する | この講座では、フィーチャモデルのフィーチャを整理する方法を紹介します。 抽象フィーチャを活用して整理する(1)フィーチャモデルを定義していると、図のようにフラットに大量のフィーチャが並ぶことがあります。これでは少し見づらいので、整理してみましょう。 抽象フィーチャを活用して整理する(2)共通フィーチャと可変フィーチャの定義を進めていくと、フラットに並ぶフィーチャの数が膨大にな... <続きを見る> |
| フィーチャ間の関係を整理する | この講座では、フィーチャモデルのフィーチャ間の関係を整理する方法を紹介します。 フィーチャ間の関係を定義するフィーチャモデルを定義していくうちに、可変なフィーチャの数が多くなってくる場合があります。この場合、後にフィーチャを選択する際の選択肢がそれだけ多くなっていると言え、それだけ選択の手間が発生することになってしまいます。これを防ぐため、後のフィーチャ選択工程で、上位フィーチャが選択... <続きを見る> |
| モデルが大きくなったら分割する | この講座では、大きくなったフィーチャモデルの分割方法を紹介します。 一つのモデルで全てを表現しない1つのフィーチャモデルで全てを表現することに拘るのは注意が必要です。例えば最初は小さかったフィーチャモデルも、定義を進めていくうちに情報量が多くなってきます。フィーチャの数が増えれば増えるほど、フィーチャモデルの全体像の把握は困難になってきます。これを防ぐため、フィーチャが増えてきてある一... <続きを見る> |
| その他フィーチャモデルを見やすくする工夫 | この講座では、フィーチャモデルの見やすさを向上させる方法を紹介します。 領域に応じて色を分けるフィーチャモデルも情報量が増加してくると、閲覧中にどこのレイヤを確認していたかわからなくなることがあります。このような見づらさを改善するため、様々な工夫が考えられます。例えばフィーチャの領域ごとに、フィーチャの背景色を設定するなどというアイデアが考えられます。領域毎に設定する背景色についてはロ... <続きを見る> |
| フィーチャが重複した時は | この講座では、フィーチャモデル上でフィーチャが重複した場合の表現方法を紹介します。 フィーチャが重複した際の表現方法フィーチャモデルを定義していると、フィーチャが重複する場合があります。例えば、複数機能間で共有する共通機能が出てきたような場合です。例ではCanType1からCanType3までの実装方式の中で、実装方式によって共通のチェック機能を搭載しているとします。ここで親子関係を素... <続きを見る> |
《フィーチャモデルとコア資産の具体的な対応の取り方》
| コンテンツ名 | 内容 |
|---|---|
| フィーチャモデルと要求仕様書の対応 | この講座では、コア資産の一部である要求仕様書とフィーチャモデルの間の、具体的な対応の取り方について説明します。 要求仕様書の位置付け要求仕様書とは、システムやソフトウェアの要件分析・要件定義工程における成果物です。要求仕様書はコア資産の一部であり、他の成果物と同様にフィーチャと対応付けて登録・更新されます。本講座では要求仕様書の記述形式がExcelおよびUSDMであることを前提として説... <続きを見る> |
| フィーチャモデルとアーキテクチャモデルの対応 | この講座では、コア資産の一部であるアーキテクチャモデルとフィーチャモデルの間の、具体的な対応の取り方について説明します。 アーキテクチャモデルの位置付けアーキテクチャモデルとは、システムやソフトウェアの設計工程における成果物です。アーキテクチャモデルはコア資産の一部であり、他の成果物と同様にフィーチャと対応付けて登録・更新されます。本講座ではアーキテクチャモデルの記述形式が、有償ツール... <続きを見る> |
| フィーチャモデルとシミュレーションモデルの対応 | この講座では、コア資産の一部であるシミュレーションモデルとフィーチャモデルの間の、具体的な対応の取り方について説明します。 シミュレーションモデルの位置付けシミュレーションモデルとは、システムやソフトウェアの設計工程における成果物です。シミュレーションモデルはコア資産の一部であり、他の成果物と同様にフィーチャと対応付けて登録・更新されます。本講座ではシミュレーションモデルの代表例として... <続きを見る> |
| フィーチャモデルとコードの対応 | この講座では、コア資産の一部であるコードとフィーチャモデルの間の、具体的な対応の取り方について説明します。 コードの位置付けコードとは、ソフトウェアの実装工程における成果物です。コードはコア資産の一部であり、他の成果物と同様にフィーチャと対応付けて登録・更新されます。 コードの管理方法一覧コア資産におけるコードの管理方法の例には以下のようなものがあります。 A)フォルダ単位で... <続きを見る> |
| フィーチャモデルとその他ドキュメントの対応 | この講座では、コア資産の一部であるドキュメントとフィーチャモデルの間の、具体的な対応の取り方について説明します。 ドキュメントの位置付け本講座で対象とするドキュメントとは、開発の各工程で定義される仕様書や解説書を指します。例えばテスト仕様書やツール解説書、検証会用のWord資料などが該当します。これらもコア資産の一部として、他の成果物と同様に、フィーチャと対応して管理されます。 ... <続きを見る> |
《SPL開発における要件定義のポイント》
| コンテンツ名 | 内容 |
|---|---|
| 【未】コア資産における非機能要求の記述方法 | <続きを見る> |
《SPL開発におけるアーキテクチャ設計のポイント》
| コンテンツ名 | 内容 |
|---|---|
| 【未】カスタムステレオタイプ(vp, variant) | <続きを見る> |
| 【未】可変要素にアイコンを付ける | <続きを見る> |
| 【未】親子関係の可視化 | <続きを見る> |
| 【未】可変性の可視化をやりすぎない | <続きを見る> |
| 【未】フィーチャと対応を取るフィールドを組織で統一する | <続きを見る> |
| 【未】ある程度の重複を妥協してパッケージを分ける | <続きを見る> |
| 【未】可変なコンポーネントのIFを共通化する | <続きを見る> |
| 【未】バインディングタイムの種類を定義する | <続きを見る> |
《SPL開発におけるシミュレーションモデル実装のポイント》
《SPL開発におけるHandCode実装のポイント》
《SPL開発におけるプロセス定義のポイント》
| コンテンツ名 | 内容 |
|---|---|
| 【未】後にテーラリングしやすいベースプロセスを定義する | <続きを見る> |
| 【未】ドメイン/アプリケーションエンジニアリングを区別する | <続きを見る> |
《SPL開発の失敗事例(アンチパターン)》
| コンテンツ名 | 内容 |
|---|---|
| 周囲の協力が得られない | この講座では、ある開発現場における、SPL開発導入の失敗事例をご紹介します。 状況今回ご紹介する現場は、ある組込みファミリ製品を開発・販売している会社です。ソフトウェア開発費が劇的に増加したのがきっかけでSPL導入を検討することとなりました。SPL導入を検討していたのは社内の事業部ではなく、横串組織に所属するソフトウェア工学実践者であり、独学でSPL開発を勉強することとなります。推進者... <続きを見る> |
| 想定したほどの生産性が出ない | この講座では、ある開発現場における、SPL開発導入の失敗事例をご紹介します。 状況今回ご紹介する現場は、ある組込み製品を開発している企業で、SPL開発を推進していました。順調に推進することができ、ハイエンド系の製品群に関して、SPL開発に成功することができました。このハイエンドの実績に自信をつけた結果、勢いはそのままローエンド系の製品群についても、同じ製品群に取り込もうとスコープを拡大... <続きを見る> |
| 一向に生産性/品質が上がらない | この講座では、ある開発現場における、SPL開発導入の失敗事例をご紹介します。 状況今回ご紹介する企業では、部品開発組織と製品開発組織を分離してSPL開発を推進していました。部品開発組織の名称はもともと「共通開発チーム」と呼ばれていました。みなさんの会社にも同様の組織はあるのではないでしょうか。分離した組織はそれぞれ・部品開発組織は部品と部品利用のためのツールを提供し、・製品開発組織はそ... <続きを見る> |
| 微妙に異なる同じ機能が何度も実装されている | この講座では、ある開発現場における、SPL開発導入の失敗事例をご紹介します。 状況今回ご紹介する企業では、機能ブロック単位に組織を構成してSPL開発を推進していました。ここで言う機能とは、アーキテクチャ上のコンポーネントに対応します。構成した組織ではそれぞれ再利用部品と製品の開発を同時並行で実施していましたが、これが後に問題を引き起こすことになります。 症状組織を分離してSP... <続きを見る> |
| 個別最適開発にした方が生産性が高くなった | この講座では、ある開発現場における、SPL開発導入の失敗事例をご紹介します。 状況今回ご紹介するのは、同一業界に属する2社が、全く別の戦略で同タイプの製品群を開発したケースです。各社それぞれの戦略を見てみましょう。 A社はSPL開発を適用し、プラットフォームの共通化を選択しました。開発対象の製品群の共通部分を部品化し、製品群に属する各製品の開発担当者に提供することで、開発の効率化を目... <続きを見る> |
| 進捗が全く進まなくなった | この講座では、ある開発現場における、SPL開発導入の失敗事例をご紹介します。 状況今回ご紹介する企業では、優秀なメンバーをアーキテクトとして招集してSPL開発を推進していました。アーキテクトはPLアーキテクチャを構築し、そこで定義されたコンポーネントそれぞれの担当チームに並行開発を指示しました。 症状コンポーネント開発を開始して以降、一向にソフトウェアが出来上がる気配がしなく... <続きを見る> |
《SPL開発の事例(弊社)》
| コンテンツ名 | 内容 |
|---|---|
| 車両統括制御システム(自動車会社A) | この講座では、ある自動車会社の車両統括制御システムを開発する組織における、SPL開発の導入事例をご紹介します。 開発対象のシステム(1)今回ご紹介する組織は、主に2つのシステムの開発を担当している部署です。1つ目は車両統括制御システムです。こちらは車の脳を司るような位置づけのシステムであり、パワートレイン、ブレーキ、ボデーやステアリングなど、車を構成する主要なシステムの動作を統括して制... <続きを見る> |
| ボデーシステム(自動車会社B) | この講座では、ある自動車会社のボデーシステムを開発する組織における、SPL開発の導入事例をご紹介します。 開発対象のシステム(1)今回ご紹介する組織は、ボデーシステムの開発を担当している部署です。ボデーシステムとは、車のヘッドライトやインテリアライト、ドアロックやセキュリティアラーム、パワーウインドウやシート、ハンドルなど、様々な装備品の動作を統括して制御するのが主な役割となります。 ... <続きを見る> |
| シフトバイワイヤシステム(自動車会社C) | この講座では、ある自動車会社のシフトバイワイヤシステムを開発する組織における、SPL開発の導入事例をご紹介します。 開発対象のシステム(1)今回ご紹介する組織は、シフトバイワイヤシステムの開発を担当している部署です。シフトバイワイヤシステムとは、車のトランスミッションのシフト操作を、電気信号とモーター等のアクチュエーターで実現する仕組みのことです。メカ式と比べて力を入れずに確実なシフト... <続きを見る> |
| エンジン制御ソフトウェア(自動車部品会社D) | この講座では、ある自動車部品会社のエンジン制御ソフトウェアを開発する組織における、SPL開発の導入事例をご紹介します。 開発対象のソフトウェア(1)今回ご紹介する組織は、エンジン制御ソフトウェアの開発を担当している部署です。エンジン制御ソフトウェアとは、ドライバのアクセル操作に応じてドライバが要求する駆動力を推定し、その要求に見合う駆動力をエンジンで生成するためにエンジン内部に噴射する燃料... <続きを見る> |
| モーター制御システム(自動車部品会社E) | この講座では、ある自動車部品会社のモーター制御システムを開発する組織における、SPL開発の導入事例をご紹介します。 開発対象のシステム(1)今回ご紹介する組織は、モーター制御システムの開発を担当している部署です。モーターは車や船舶、産業機械など様々な場所で利用されており、パワーの必要な大型モーターからドローンに搭載される小型モーターに至るまで様々なモーターが存在します。今回ご紹介する組織で... <続きを見る> |
| インバータ制御システム(自動車部品会社F) | この講座では、ある自動車部品会社のインバータ制御システムを開発する組織における、SPL開発の導入事例をご紹介します。 開発対象のシステム(1)今回ご紹介する組織は、インバータ制御システムの開発を担当している部署です。インバータは、主にハイブリッドカーや電気自動車の駆動力を生み出すモーターに対して、バッテリから流す電力を制御するシステムです。モーターを早く回転させたい時には大きな電流を、遅く... <続きを見る> |
| DC/DCコンバータ制御ソフトウェア(自動車部品会社G) | この講座では、ある自動車部品会社のDC/DCコンバータ制御ソフトウェアを開発する組織における、SPL開発の導入事例をご紹介します。 開発対象のソフトウェア(1)今回ご紹介する組織は、DC/DCコンバータ制御ソフトウェアの開発を担当している部署です。DC/DCコンバータは、ハイブリッドカーや電気自動車等に搭載される、モーターを動かすバッテリの高電圧を低電圧に降圧し、他の電装品であるライトやワ... <続きを見る> |
《SPL開発の事例(国内)》
《SPL開発の事例(海外)》
《研究動向》
| コンテンツ名 | 内容 |
|---|---|
| 【未】SPLC2020 | <続きを見る> |
| 【未】GfSE | <続きを見る> |
| 【未】EAST-ADL-Specification_V2.1.12 | <続きを見る> |
《成果物テンプレート》
| コンテンツ名 | 内容 |
|---|---|
| 【未】SPL開発向けUSDM | <続きを見る> |
《コラム》
| コンテンツ名 | 内容 |
|---|---|
| プレゼン資料のSPL化で業務効率を改善してみた | このコラムでは、弊社内で行われている業務効率改善のアイデアの一つである、日々活用する資料のSPL化についてご紹介します。 弊社メンバーの困りごと(1)まず、弊社メンバーの困りごとをご紹介します。弊社では、様々な開発現場の設計改善を支援するコンサルティングサービスを主に提供しています。日々のコンサルティング支援の特徴として、様々な業種のお客様と関わる機会があります。それらお客様全てに毎回... <続きを見る> |