[2023.10.20]新規追加コンテンツのお知らせ
いつもEureka Boxをご利用頂き、ありがとうございます。
今週の新規追加コンテンツは、「おすすめのプレイリスト」、「MBD学習」、「SPLリファレンス」、「ドメインモデリング演習」です。
おすすめのプレイリスト
「Eureka Boxによるサポート」
【製造業DXとEureka Box】カテゴリーに「Eureka Boxによるサポート」を追加しました。
これまでの講座を通じて、ソフトウェアファーストを実現するためには何をしなければならないか、そのためにはどのようなものが必要かを見てきました。今回は、それらを実現するためにEureka Boxが何を提供しているかを紹介します。
MBD学習
「Simulink モデル構成要素のパラメータ取得・設定」

【API を使った効率化/API の基礎】カテゴリーに「Simulink モデル構成要素のパラメータ取得・設定」を追加しました。
先月はAPIを用いてSimulinkモデルの構成要素を検索する方法を説明しました。今回はその要素に対して、パラメータを取得したり設定したりする部分を取り上げます。ここまで来れば、モデリングにまつわる多くの作業が自動化できます。ぜひ実業務でも活用してみてください。
SPL学習
「ツールチェーンの検討」
【アドバンスト/SPL開発をリードするために】カテゴリに「ツールチェーンの検討」を公開しました。
ツールチェーンとは、ある目的を達成するために組み合わせて使用するツール一式のことです。SPL開発におけるツールチェーンはどのような条件を満たすものでなければならないか、どうやってツールチェーンを選べばよいかを解説します。なお、詳細なツールの選定事例については、別途ご紹介する予定です。
ドメインモデリング演習
「【10/20の課題】歩数計」

歩数計のドメインモデルを書いてみましょう。解答の締め切りは11月12日です。その後、一週間程度で解答例・解説を公開する予定です。ご解答をお待ちしています!
「【10/20の課題】歩数計」
「【10/20の課題】歩数計」(体験版)
また、「【9/22の課題】電子レンジ」の解答例も
...[2023.10.06]新規追加コンテンツのお知らせ
いつもEureka Boxをご利用頂き、ありがとうございます。
今週の新規追加コンテンツは、「おすすめのプレイリスト」、「MBD学習」、「SPLリファレンス」です。
おすすめのプレイリスト
「リスキリング」
【製造業DXとEureka Box】カテゴリーに「リスキリング」を追加しました。
仮説検証型で開発を行い、開発を内製化するには、そのための人材を確保する必要があります。今回は、どのような人材が必要になるのか、その人材を育成するにはどうすればよいのかを解説します。
MBD学習
「Simulinkモデルのデバッグ方法」

【制御モデルの開発 (アルゴリズムの設計と実装)/Simulink モデルのデバッグ】カテゴリーに「Simulinkモデルのデバッグ方法」を追加しました。
今回は、Simulinkモデルをデバッグする方法を取り上げます。Simulinkには、「シミュレーションステッパー」と「Simulinkデバッガー」という、デバッグのための機能が用意されています。2つを比較したあと、主に前者について、詳しい手順も紹介します。
SPL学習
「SPL開発とXDDP」
【アドバンスト/他手法との連携】カテゴリに「SPL開発とXDDP」を公開しました。
XDDPとは変更開発におけるモレ・ミス・ムダを防止するプロセスです。SPL開発においても、変更開発が発生した際にはXDDPを活用することができます。XDDPをどう適用するか、SPL開発と通常開発とで適用の仕方がどう違うかを紹介します。
今後も、コンテンツは定期的に新規追加・更新してまいります。
引き続き、Eureka Boxをよろしくお願いいたします。
[2023.10.03]新規追加コンテンツのお知らせ
いつもEureka Boxをご利用頂き、ありがとうございます。
本日の新規追加コンテンツは「XDDP学習」です。「USDM演習」も9/25の課題を公開済みです。
XDDP学習
「一斉にソースコードを変更する」
「ソースコード変更後の確認」
【ベーシック/変更のプロセス】カテゴリにソースコード変更に関するコンテンツを公開しました。
変更箇所を調査し、変更要求仕様書、トレーサビリティ・マトリクス、変更設計書を作成してレビューも済んだら、いよいよソースコードの変更です。どのように変更するかとその理由、変更が正しく行われたかの確認について、2つのコンテンツで説明します。
「一斉にソースコードを変更する」
「ソースコード変更後の確認」
USDM演習
「【9/25の課題】スマート扇風機の要求仕様」

スマート扇風機の要求仕様を書いてみましょう。システムの前提や制約、問題以外の要求仕様は自由に設定してください。解答例・解説は10月25日頃に公開する予定です。ご解答をお待ちしています!
「【9/25の課題】スマート扇風機の要求仕様」
「【9/25の課題】スマート扇風機の要求仕様」(体験版。お題のみ)
また、「【8/25の課題】サイクルコンピュータの要求仕様」の解答例も公開しています。
今後も、コンテンツは定期的に新規追加・更新してまいります。
引き続き、Eureka Boxをよろしくお願いいたします。
[2023.09.22]新規追加コンテンツのお知らせ
いつもEureka Boxをご利用頂き、ありがとうございます。
今週の新規追加コンテンツは、「おすすめのプレイリスト」、「ドメインモデリング演習」および体験版、「ドメインモデリング学習」、「SPLリファレンス」です。また、MBD学習の動画コンテンツの追加も開始しています。
おすすめのプレイリスト
「仮説検証型と内製化」
【製造業DXとEureka Box】カテゴリーに「仮説検証型と内製化」を追加しました。
DXによって顧客に最適な価値を提供するには、ソフトウェアファーストへ移行することが重要であり、そのためには、新しい開発スタイルが必要です。その際に必要な2つの移行「仮説検証型アジャイル開発への移行」と「外注していた開発プロセスの内製化」について説明します。
ドメインモデリング演習
「【9/22の課題】電子レンジ」
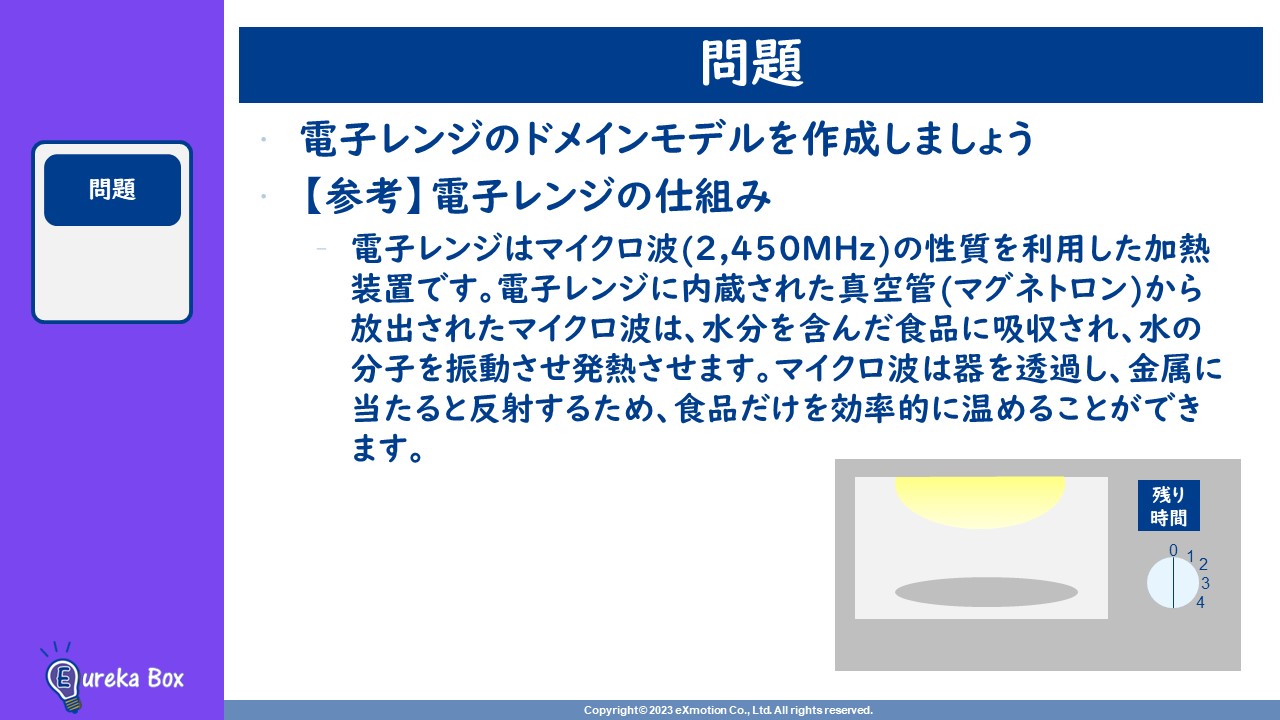
「ドメインモデリング演習」コースおよび体験版を新規公開しました。
ドメインモデリング学習で学んだ5つのステップに沿ってモデリングをしてみましょう。初回の課題は「電子レンジ」です。詳細は「演習コースの使い方」のコンテンツをご覧ください。
「【9/22の課題】電子レンジ」
「演習コースの使い方」
「【9/22の課題】電子レンジ」(体験版)
「演習コースの使い方」(体験版)
ドメインモデリング学習
「ドメインモデリングの落とし穴」
【ベーシック/具体例で考える「良いモデルとは」】カテゴリに「ドメインモデリングの落とし穴」を公開しました。
「ドメインモデリングとは」の講座で、洗濯として行った結果だけを表現してしまったモデルを紹介しました。他にも、ドメインモデルを作成するつもりが「結果」をモデリングしてしまう例はよく見られます。ここでは、「自動販売機」を例に、ついはまってしまいがちな結果中心のモデルの落とし穴について、具体的なモデルを取り上げながら解説します。
SPLリファレンス
「フィーチャモデルの解説書を作成する」
【Tips/可変性分析・フィーチャモデリングのポイント】カテゴリに「フィーチャモデルの解説書を作成する」を公開しました。
フィーチャモデルは、対象の製品群が持つ可変性の全体像をシンプルに表現できるという点で、非常に有用なアイテムです。しか
[2023.09.08]新規追加コンテンツのお知らせ
いつもEureka Boxをご利用頂き、ありがとうございます。
今週の新規追加コンテンツは、「おすすめのプレイリスト」、「XDDP学習」、「MBD学習」、「SPLリファレンス」です。
おすすめのプレイリスト
「ソフトウェアファースト」
【製造業DXとEureka Box】カテゴリーに「ソフトウェアファースト」を追加しました。
これから製造業DXについての一連のコンテンツを公開していきます。
DXが大切だと言われても、これまでハードウェア中心に進んできた製造業において、ソフトウェア開発現場の人たちは何か他人事のような気がしているかもしれません。しかし、DXによって顧客に最適な価値を提供するには、ソフトウェアファーストへ移行することが重要です。初回のこのコンテンツでは、「ソフトウェアファースト」について紹介します。
XDDP学習
「変更仕様に対する変更方法を決定する」
「変更設計書のケース別作成方法」
「変更方法の確認」
「変更設計書の注意点」
【ベーシック/変更のプロセス】カテゴリーに、変更設計書についての4つのコンテンツを公開しました。
変更設計書は、XDDPの3つの成果物のうち、変更要求仕様書、トレーサビリティ・マトリクスに続く最後の成果物です。What、Where、Howの「How」を表現する変更設計書とは具体的にどのようなものなのか、どう書けばよいのか、注意点は何か、などを紹介します。
「変更仕様に対する変更方法を決定する」
「変更設計書のケース別作成方法」
「変更方法の確認」
「変更設計書の注意点」
MBD学習
「Simulink モデル構成要素の検索」

【API を使った効率化/API の基礎】カテゴリに「Simulink モデル構成要素の検索」を公開しました。
APIを用いて作業を自動化するにあたり、まず、扱う対象となるSimulinkモデルの構成要素を特定する必要があります。今回は、特定の条件に合致するSimulinkモデルの構成要素を検索する手段として、関数find_system、Simulink.findBlocks、Simulink.findBlocksOfTypeの使い方を紹介します。
SPLリファレンス
「SPL開発の標準プロセス
...[2023.08.25]新規追加コンテンツのお知らせ
いつもEureka Boxをご利用頂き、ありがとうございます。
今週の新規追加コンテンツは、「UML学習」、「USDM演習」、「MBD学習」、「SPLリファレンス」です。
UML学習
「アイス:多重度、ロール名」
「照明:状態マシン図」
【表記サンプル】カテゴリーに、「アイス:多重度、ロール名」と「照明:状態マシン図」を追加しました。プレ公開版のうち、まだ「UML学習」コースに入っていなかった2つの例題コンテンツに対応するものです。
※これに伴い、「UML学習【プレ公開版】」は近く公開を停止する予定です。
USDM演習
「【8/25の課題】サイクルコンピュータの要求仕様」
サイクルコンピュータの要求仕様を書いてみましょう。システムの前提や制約、問題以外の要求仕様は自由に設定してください。解答例・解説は9月25日頃に公開する予定です。ご解答をお待ちしています!
「【8/25の課題】サイクルコンピュータの要求仕様」
「【8/25の課題】サイクルコンピュータの要求仕様」(体験版。お題のみ)
また、「【7/25の課題】映写機システムの要求仕様」の解説・解答例も公開しています。
MBD学習
「スタイルの重要性」

【制御モデルの品質向上/スタイルガイドラインの適用】カテゴリに「スタイルの重要性」を公開しました。
モデル品質の中でも重要な「保守性」を高めるには、「解析性」=「読みやすさ」を向上させる必要があります。このコンテンツでは「読みやすさ」の重要性と、情報デザイン分野で使われている「読みやすさ」の指標を参考に、「読みやすさ」に配慮したモデルの書き方(スタイル)や改善のヒントを紹介します。
SPLリファレンス
「標準プロセスのプロダクトライン化(Process Product Line)」
【Tips/プロセス定義のポイント】カテゴリに「標準プロセスのプロダクトライン化(Process Product Line)」を公開しました。
標準プロセスを定義しても、期待していたほど開発現場から使ってもらえない(再利用してもらえない)ケースが多く見かけられます。この場合の標準プロセスの再利用に関する問題は
[2023.08.17]新規追加コンテンツのお知らせ
いつもEureka Boxをご利用頂き、ありがとうございます。
今週は「XDDP学習」のコンテンツを4本公開しました。
XDDP学習
「変更仕様に対する変更箇所を特定する」
「変更要求TMにおける列方向の書き方」
「変更要求TMの作成方法」
「変更要求TMにおける注意点」
【ベーシック】の【変更のプロセス】カテゴリーに、変更プロセスのうち「特定」に関する4つのコンテンツを公開しました。
変更箇所を特定する方法の概要と、トレーサビリティ・マトリクス(TM)の列にはどのように成果物を並べるのか、TMの中身はどう記入するのか、その際の注意点は何かをご紹介します。
「変更仕様に対する変更箇所を特定する」
「変更要求TMにおける列方向の書き方」
「変更要求TMの作成方法」
「変更要求TMにおける注意点」
今後も、コンテンツは定期的に新規追加・更新してまいります。
引き続き、Eureka Boxをよろしくお願いいたします。
[2023.08.04]新規追加コンテンツのお知らせ
いつもEureka Boxをご利用頂き、ありがとうございます。
今週の新規追加コンテンツは、「使いやすさとUXを実現するための人間中心設計プロセス講座 基礎編 By U’eyes Design」、「ドメインモデリング学習」、「SPLリファレンス」です。「USDM演習」も7/25の課題を公開済みです。
使いやすさとUXを実現するための人間中心設計プロセス講座 基礎編 By U’eyes Design
「ユーザー評価手法の紹介」
「ユーザー評価の手続きと観点」

【STEP4 検証:要求に対する評価】として、「ユーザー評価手法の紹介」と「ユーザー評価の手続きと観点」を公開しました。
「ユーザー評価手法の紹介」では、ユーザビリティ評価とはどういうものか、というところから、評価手法の特徴、メリット・デメリットについてお伝えします。そして、「ユーザー評価の手続きと観点」では、ユーザビリティテストの具体的な実施方法の解説を行います。
※「使いやすさとUXを実現するための人間中心設計プロセス講座 【基礎編】 」は今回が最終回です。
ドメインモデリング学習
「Step3:それらの特徴は何か?」
「Step4:互いの関係はどうなっているか?」
「Step5:ドメインモデルを表現する」

【ベーシック】の【ドメインモデリングのプロセス】カテゴリーに、「Step3:それらの特徴は何か?」、「Step4:互いの関係はどうなっているか?」、「Step5:ドメインモデルを表現する」を公開しました。
前回検討した「目的」と「扱うもの」を基に、それらの特徴、互いの関係を検討し、最終的にUMLのクラス図に整理します。漠然としていた概念がモデルの形にまとまっていきます。ご自身でもぜひ手を動かしてみてください。
「Step3:それらの特徴は何か?」
「Step4:互いの関係はどうなっているか?」
「Step5:ドメインモデルを表現する」
SPLリファレンス
「スケジューラーのコア資産化」
【Tips/HandCode実装のポイント】カテゴリに「スケジューラーのコア資産化」を公開しました。
SPL開発で扱うコードにおけるスケジューラーは、コード上に点在する可変性を考慮して呼び出し順を規定する必要があります。そのためスケ
[2023.07.21]新規追加コンテンツのお知らせ
いつもEureka Boxをご利用頂き、ありがとうございます。
今週の新規追加コンテンツは、「ドメインモデリング学習」、「使いやすさとUXを実現するための人間中心設計プロセス講座 基礎編 By U’eyes Design」、「MBD学習」、「SPLリファレンス」です。
ドメインモデリング学習
「Step1:目的は何か?」
「Step2:そこで何を扱うのか?」

【ベーシック】の【ドメインモデリングのプロセス】カテゴリーに、「Step1:目的は何か?」および「Step2:そこで何を扱うのか?」を公開しました。
【ドメインモデリングのプロセス】では、対象をモデルによって抽象化する「ドメインモデリング」について、具体的なプロセスを5つのステップに分けて紹介します。今回は、Step1とStep2を解説します。
「Step1:目的は何か?」
「Step2:そこで何を扱うのか?」
【体験版】「Step1:目的は何か?」
使いやすさとUXを実現するための人間中心設計プロセス講座 基礎編 By U’eyes Design
「ユーザインタフェースの設計原則」
「各種プロトタイプの作成方法」

【STEP3 制作:設計解決案の作成】として、「ユーザインタフェースの設計原則」と「各種プロトタイプの作成方法」を公開しました。
ここからはいよいよユーザーの要求を形にしていくフェーズに入ります。「ユーザインタフェースの設計原則」では、情報の把握、構造化、可視化、分析と改善など、UIデザインのプロセスを紹介します。「各種プロトタイプの作成方法」では、その中から、情報の構造化、フローの描き方に注目してポイントを解説していきます。
「ユーザインタフェースの設計原則」
「各種プロトタイプの作成方法」
MBD学習
「Simulink モデル構成要素と識別子」

【API を使った効率化/API の基礎】カテゴリに「Simulink モデル構成要素と識別子」を公開しました。
APIを用いたプログラムでSimulinkモデルの構成要素を扱う場合、識別子を使ってその要素を特定します。このコンテンツでは、ハンドル、パス、Simulink識別子という3つの識別子について特徴やメリット・デメリットを解説し、実際の開発においてどのように使い分けるとよいかを紹介します。
「Simulin...
「ソフトウェアテスト presented by バルテス」コースの公開終了について
いつもEureka Boxをご利用頂き、ありがとうございます。
バルテス株式会社のQbookアカデミーのサービス終了に伴い、 「ソフトウェアテスト presented by バルテス」

